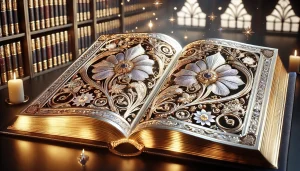江戸時代の大坂における商家の物語
商家における呼称の紹介
NHKの特選時代劇として再放送されている「あきない世傳(せいでん)金と銀」と、NHKBS時代劇として放送される予定の「あきない世傳(せいでん)金と銀 2」は、江戸時代中期の大坂天満にある呉服商・五鈴屋を舞台として、ご寮さんの幸(さち・小芝風花)が商売で活躍する話です。
そのため物語の中では、どの立場の人がどんな呼ばれ方をしているのか頻繁に描写されています。今回の記事では、そんな江戸時代の大坂において、商家の人々の呼称や名前の付け方についてご紹介します。
主筋(主家)と奉公人の関係
同族経営が当たり前の江戸時代の商家
「主筋(主家)」とはつまり主人とその一家のことです。もちろん現代でも「一族経営」という言葉がたまに使われるように、経営者が同じ家族や一族の人間で行われることもあります。
しかし江戸時代ではさらにその性質は強く、同族で経営することが当たり前でした。
主筋(主家)と奉公人の差別
武家が血のつながりを重視していたように、商家も同じく血のつながりを重視ししており、商家と一族とそれ以外のいわゆる「奉公人」は厳然と差別されて封建的な関係にあります。
例を挙げると奉公人は当主の許しがなければ、奉公人は結婚をして所帯を持つこともできませんでした。
江戸時代 大坂における商家の主筋の敬称
主筋の人たちの呼称一覧
江戸時代の江戸でも主人のことを「旦那(だんな)」やその妻のことを「女将(おかみ)」と呼びますが、大坂ではそういう敬称に上方方言が加わり、江戸とは異なる独特の呼び方になっています。
下記の表では当主夫婦を基本として、その上に先代の両親と当主に三兄弟・三姉妹がいる商家を想定したときの呼び方です。
| 呼び方 | 読み方 | 立場 |
|---|---|---|
| 旦那さん | だんさん | 商家の当主 |
| ご寮さん | ごりょんさん | 当主の妻 |
| 親旦那さん | おやだんさん | 当主の父親 |
| お家さん | おえさん | 当主の母親 |
| 兄ぼんさん | あにぼんさん | 当主の長男 |
| 中ぼんさん | なかぼんさん | 当主の次男 |
| 小ぼんさん | こぼんさん | 当主の三男 |
| 姉いとさん | あねいとさん | 当主の長女 |
| 中いとさん | なかいとさん | 当主の次女 |
| 小いとさん | こいとさん | 当主の三女 |
「あきない世傳(せいでん) 金と銀」では主人公・幸(小芝風花)は、五鈴屋の四代目徳兵衛に嫁いで以来は、当主の妻として奉公人たちから「ご寮さん」と呼ばれるようになります。
主筋の人たち そのほかの呼び方
これらの呼び方以外にも当主の息子を単に「ぼんぼん」と呼んだり、また名前が「惣次」という名前であれば「惣ぼん」さんと呼ぶことこもあったようです。
また当主の娘であれば長女を「嬢さん(とうさん)」、末娘であれば「こいとさん」を縮めた言い方の「こいさん」と呼ばれることもありました。
江戸時代 大坂における奉公人の呼称
奉公人の呼称一覧
| 呼び方 | 読み方 | 立場 |
|---|---|---|
| 番頭さん | ばんとうさん | 男性奉公人のトップで奉公人たちのまとめ役。平時の営業責任者 |
| 手代 | てだい | 男性の奉公人。客と商談ができる |
| 丁稚 | でっち | 男性の奉公人。客と商談はできない見習いの立場。店先では単に「子ども」と呼ばれる |
| 女衆 | おなごし | 女性の奉公人。主家のプライベート空間で働き、店に出ることはない |
男性奉公人 名前の付け方
男子が商家に奉公に上がるとそれまでの名前から商家風の名前に改められます。五鈴屋では名前の下に、丁稚であれば「吉」が、手代であれば「七」、番頭であれば「助」がつけられます。
例えば「賢輔(けんすけ)」という子どもが五鈴屋に奉公に上がると、「賢吉」という名前に改められます。もしこの賢吉が手代に昇格すれば、次は「賢七(けんしち)」に、さらに番頭に昇格すれば「賢助」という具合に名前が変わっていきます。
女性奉公人 名前の付け方
女子も商家に女衆として奉公に上がると、男子と同じくやはり名前が改められます。しかし男子と比べると名前の付け方は雑で、「松」・「竹」・「梅」のいずれかをつけられます。
奉公が終わるまで同じ名前で、主筋や他の奉公人たちから「お松どん」・「お竹どん」・「お梅どん」と呼ばれることになったようです。
女衆の「幸」はなぜ名前を改められなかったのか?
ちなみに「あきない世傳(せいでん) 金と銀」の主人公・幸は最初に女衆として五鈴屋に奉公に上がりますが、名前は改められることなく「幸(さち)」のままでした。
これはそのときに五鈴屋の女衆が使っていなかった名前が「松」であり、新入りの幸が「お竹どん」と「お梅どん」を飛び越えて「松」の名前を使うことを憚られたため、「幸」のままで通したという経緯があります。