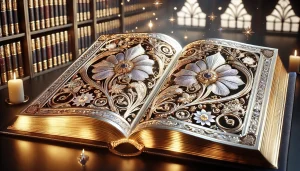あきない世傳(せいでん)金と銀は大坂商人のお話
「あきない世傳(せいでん)」の人たちは何を食べていたのか?
NHK特選時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀」とNHKBS時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀 2」は、江戸時代中期、大坂天満の呉服商・五鈴屋を舞台として幸(小芝風花)が活躍するドラマです。
ドラマでは大坂商人の日常生活が描かれるため、当時の商家の人たちの食事に関する描写も頻繁に登場します。お金を稼ぐことが使命の商人ですから、豪華な食事をしていたのかどうか気になるところです。
大阪商人たちの食事は質素だった
ところが江戸時代の大坂の商家に関する資料を確認すると、商家の人たちは豪勢な食事とはほとんど無縁で、かなり質素な食事をしていたと言われています。
実際に小説版「あきない世傳(せいでん)金と銀」の(一)・(二)・(三)を読んだだけでも、商家の奉公人たちだけでなく、当主の一族でさえも日頃の食事は、「これで体が保つのか?」と思えるほどの食事をしていたことが描写されています。
今回の記事では「あきない世傳(せいでん)金と銀」の舞台となった大坂天満の五鈴屋を通して、当時の商家の人たちは何を食べていたのか紹介します。
あきない世傳(せいでん)金と銀 日常の食事メニュー
五鈴屋 通常の食事メニュー
江戸時代中期の大坂の商家では、多くの場合、昼食の前にお米を炊いていたようです。そのため一日の食事は昼を起点として始まっていました。
小説版「あきない世傳(せいでん) 金と銀」(源流篇)で登場するある日のメニューは次の通りとなります。
| 主菜 | おかず(副菜) | |
|---|---|---|
| 昼食 | 炊き立てのご飯 | 香々(こうこ)・煮物 |
| 夕食 | お茶漬け | 香々(こうこ) |
| 朝食 | 茶粥 | 香々(こうこ) |
現代日本人の感覚からすると「たったこれだけ」と思われるかもしれませんが、本当にたったこれだけです。この食事メニューは商家の当主も、新入りの丁稚も同じです。
香々(こうこ)とは
香々(こうこ)とは漬物のことです。五鈴屋では、香々のために地元で採れる天満大根の身の部分を使っています。
一年分を食べられるように冬場にまとめて漬けています。また天満大根の茎の部分は「おくもじ」として茎漬けにして食べられます。
煮物について
お昼のおかずとしてつけられている煮物とは、主に野菜の煮物であると考えられます。やはり天満大根が煮物の具として使われたほか、煮物の代わりに辛子菜の味噌和えなどもメニューになっていたようです。
茶粥
朝食として翌朝に食べられる茶粥の茶は、その前の夕食の時に使われたお茶漬けの茶がらが使われます。
五鈴屋 毎月朔日(一日)と十五日の食事メニュー
小説版「あきない世傳(せいでん) 金と銀」では、正月・お祭り以外の日は、上記のようなメニューが続きます。しかし四代目徳兵衛に最初の妻である、紅屋の菊栄が嫁いできた頃から少し変わります。
船場の習慣に合わせて、毎月朔日(一日)と十五日の食事メニューに魚がつくようになります。小説版「あきない世傳(せいでん) 金と銀」(二)(早瀬篇)の内容にもとづいて、魚がつくときの一日のメニューはこのようになると推測できます。
| 主菜 | おかず(副菜) | |
|---|---|---|
| 昼食 | 炊き立てのご飯 | 香々(こうこ)・鯖の煮付け |
| 夕食 | お茶漬け | 香々(こうこ)・鯖の粗と大根を合わせた汁物 |
| 朝食 | 茶粥 | 香々(こうこ) |
昼食時につく魚について
昼食のおかずに供される魚とは、鯖・鰯・鯵などいわゆる青魚がメインで、比較的安価な魚が出されていたようです。
ただ、奉公人たちにとって普段の楽しみは食べることなので、食事にたまに魚がつくことは大変な励みになったと言われています。
あきない世傳(せいでん)金と銀 祝膳のメニュー
祝膳とは?
祝膳とは結婚披露宴で供される料理のことです。もちろん「ハレの日」のメニューなので、普段の食事とは全く異なったメニューが並びます。
小説版「あきない世傳(せいでん)金と銀」の(一)から(三)までに結婚披露宴の描写が3回あり、そのときのメニューが説明されていますので表にまとめます。
祝膳のメニュー
この中では最初に挙げた四代目徳兵衛と菊栄の披露宴に供されたメニューが、最も豪華であると考えられます。
これらの違いは嫁の実家が船場の小間物問屋(菊栄)であるか、豪農の下働き(幸)であるかという家格の違いが表れたものでしょう。