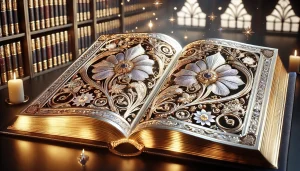あきない世傳(せいでん) 金と銀 五鈴屋の商売
五鈴屋は絹織物を商う呉服商
NHK特選時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀」とNHKBS時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀 2」は、江戸時代中期、大坂の呉服商・五鈴屋を舞台として幸(小芝風花)が活躍するドラマです。
呉服商とは、紗綾(さあや)・縮緬(ちりめん)・羽二重(はぶたえ)などの絹織物を商う商売で、江戸時代中期の大坂でどのようにこれらが販売されているか頻繁に登場します。
江戸時代の大坂における呉服商の販売方法について
そこで今回の記事では18世紀半ばの大坂において、呉服商が顧客に対してどのように反物を販売し、現金を回収していたのか紹介します。
当時の大坂の呉服商が用いた反物や帯など商品の販売形態は、「屋敷売り」・「見世物商い」・「店前現銀売り」の3つがあります。
屋敷売り・見世物商い・店前現銀売り
屋敷売り(やしきうり)
店の手代らが得意客の好みそうな反物を担いで、客の自宅で販売する方法。客から店の方に出向く必要はありません。
また商品を販売した代金は、すぐに回収せず節季(盆暮)に回収します。
見世物商い(みせものあきない)
得意客のもとに見本を先に持っていき、注文を取ってあとで品物を納める販売方法。屋敷売りと同じく客から店の方に出向く必要はありません。
また商品を販売した代金は、すぐに回収せず節季(盆暮)に回収します。
店前現銀売り(たなさきげんぎんうり)
客が直接店に出向いて品物を選びます。店側は商品を渡すのと同時に代金を回収します。
店前現銀売りの販売方法は、江戸の呉服商・越後屋の三井高利が始めたとされます。大坂では17世紀後半に高麗橋にある岩城桝屋が店前現銀売りを始めたと言われ、天満の南側にある船場地区の一部の店でこの販売方法が採られました。
屋敷売り・見世物商い・店前現銀売りの比較
屋敷売り・見世物商い・店前現銀売りという3つの販売方法を比較すると次のようになります。屋敷売り・見世物商いは、店前現銀売りと比べて支払い時期が先に延ばされるため、商品代金と支払い猶予期間分の利子が加算されます。
| 商品の販売場所 | 支払い時期 | 支払い明細 | |
|---|---|---|---|
| 屋敷売り | 得意客の自宅 | 盆暮などの節季 | 商品代金 + 利子 |
| 見世物商い | 得意客の自宅 | 盆暮などの節季 | 商品代金 + 利子 |
| 店前現銀売り | 店頭 | 品物を渡した時点 | 商品代金のみ |
五鈴屋の代金回収方法
「屋敷売り」・「見世物商い」と「大節季払い」
小説版「あきない世傳(せいでん) 金と銀」は享保年間から始まります。物語の舞台となる五鈴屋は大坂・天満に所在し、天満の呉服屋は主に「屋敷売り」と「見世物商い」の2つの販売方法が採用されていました。
また個人の得意客に販売した絹織物の代金回収は「大節季払い」と言って、年に一度、12月に回収していました。
五代目徳兵衛から「五節季払い」に
しかし五鈴屋は五代目徳兵衛(惣次)の代になると、代金の回収時期が変わります。年に一度の「大節季払い」から、年に五度の「五節季払い」に変わります。
客からすると、これまで年に一度、師走の時期にだけ支払っていた代金を、師走に加えて8月のお盆・3月3日・5月5日・9月9日にも支払ってもらうという方針になります。
反物を販売した時点から回収までのサイクルを短くするという、五代目徳兵衛の狙いは2つの効果を生みます。
- 商品代金とは別に支払っていた客の利子負担を軽くすることで販売点数を増やす
- 年に一回しかなかった現銀の流入を年に五回とすることで機動的な販売政策を打ち出す
「誓文払い」という店前現銀売り
大坂の天満では店前現銀売りはしなかった
このように同じ大坂でも船場では一部の店で店前現銀売りは採用していましたが、船場よりも北に位置する天満では店前現銀売りという代金回収方法は採用されませんでした。
これは天満では「昔ながらの得意客を大事にする」という呉服商組合の決まり事を大切にしていたからと言われています。
年に一度だけの誓文払い
しかし小説版の「あきない世傳(せいでん) 金と銀」(源流篇)で五鈴屋は、神無月二十日(11月20日)だけは「誓文払い」と言って、店前現銀売りでかつ全ての反物を半額するという販売を行っていました。
現代風にいうとこの「誓文払い」とは「バーゲンセール」ということになるでしょう。
それでも「誓文払い」は例外的な販売方法ということで、年に一度だけしかも大坂天満の呉服仲間の了承を得てから行うというものでした。