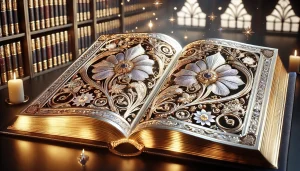あきない世傳(せいでん) 金と銀と奉公人たち
主人公・幸は女衆という女性奉公人だった
NHK特選時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀」とNHKBS時代劇「あきない世傳(せいでん) 金と銀 2」は、江戸時代中期、大坂の呉服商・五鈴屋を舞台として女主人・幸(小芝風花)が活躍するドラマです。
女主人が主人公と言っても、幸の出自は「女衆」と呼ばれる女性奉公人の身分から上がってきた人物です。またそのほかの登場人物には、五鈴屋で働く男性奉公人たちもいます。
主家と奉公人は封建的な関係
現代の日本でも会社で働く文脈で労働者のことを「奉公人」と呼んだり、同族経営のオーナー会社で忠実に働くことを「奉公する」という動詞が比喩的に使われることはあるでしょう。
しかし、江戸時代の武家や商家で一般的に見られた「主家と奉公人」の関係は、日本国憲法第14条の「法の下の平等(身分制の否定)」や、第27条「自由な労働契約の権利と義務」などによって法律として明確に否定されています。
それだけに「あきない世傳(せいでん)金と銀」で描写される「主家と奉公人」の区別は、現代の日本人にとっては奇妙でもあり、ドラマとしては興味関心の対象となるでしょう。
そこで今回の記事では、江戸時代の商家において奉公人たちの習慣となっていた事柄について紹介いたします。
商家における奉公人たちの慣わし
食事の区別
「あきない世傳(せいでん) 金と銀 江戸時代 大坂の商家の食事」という記事で主筋も奉公人も、一日三食のメニューは同じであると説明しました。食べるものが同じであったというのその通りなのですが、両者の食べる場所と食器は異なります。
主筋は座敷で脚付きのお膳を使い、女衆の給仕を受けながら食事をとっていたのに対して、奉公人たちは板敷で箱膳を使って食事をしていました。
また飯茶碗なども主筋の茶碗は大きかったのに対して、奉公人たちの茶碗は小ぶりであったと言われています。
風呂・雪隠(せっちん)の区別
江戸時代では商家の奉公人たちは「住み込み」が原則です。そのため奉公人たちは風呂や雪隠(トイレのこと)も店に備え付けのものを使う必要がありますが、主筋の人たちが使うものとは別の風呂と厠を使っていました。
例えば「あきない世傳(せいでん)金と銀」の五鈴屋であれば、風呂に関しては主筋の人たちは、家のものを使いますが、奉公人たちは町にある銭湯を使うことになります。
また雪隠についても五鈴屋の主筋は家の内部のものを使いますが、奉公人たちは庭つまり外にある雪隠で用を足すことになります。
休日について
現代の日本では労働基準法第35条に基づいて、労働者は最低でも週に1日以上の休日を取ることが法律として認められています。
しかし江戸時代の奉公人たちは、現代と違って法的に認められた休日は存在しません。主な休日は正月と盆に認められた「薮入り」がメインで、休日の数も現代よりも少なかったと考えられています。
見習い期間(丁稚)は無給
現代の日本では労働基準法第24条に基づき、雇用契約があり被雇用者が雇用主に労働を提供している場合、必ず賃金として通貨等を支払わなければなりません。
しかし、江戸時代の商家では見習いである丁稚には、主家から現金(現銀)を支払われることはありません。丁稚の期間は5年から10年ぐらいで、この間は無給で働くことになります。
衣食住・教育などの福利厚生は現物支給されていた
ただし商家の丁稚は衣食住と教育については無料です。着るものは主家から「お仕着せ(おしきせ)」と呼ばれる一種のユニフォームを与えられ、食事は賄いで、住む場所については主家に住み込みでした。丁稚は無給であっても、今でいう現物の福利厚生は受けられることになっていました。
また商家の丁稚は将来的に手代となって、実際に商品販売や代金回収の役割を分担することを期待されています。そのため商人として必要な教育(読み書き・算術・基本的なビジネススキルなど)を年長者から受けることができたようです。
結婚について
なんとなく気づく方もいらっしゃるかもしれませんが、奉公人は結婚についても当人同士の自由意志で決められません。結婚をするためには当主の許しが必要でした。
もちろん現代では結婚は日本国憲法第24条1項や民法第731条などを根拠として、当人同士の意思による自由な婚姻が認められています。
奉公人が経営にタッチするルート
主筋の場合、当主が引退したり亡くなったりするとその惣領息子が跡を継ぐというのが基本です。つまり商家の経営は血統によって引き継がれていくことになります。
では奉公人たちはどんなに商才と実績があっても、商家の経営にタッチすることはできなかったのでしょうか?当時の奉公人たちは、自分で新しく商売を始める以外に、2つのルートで商家の経営に関わることができました。
1. 主家に婿入り
1つ目の方法は息子がいない商家で、当主の娘と結婚するケースです。この場合、奉公人は主家に婿入りすることになります。
2. 別家(べっか)
2つ目の方法は別家(べっか)として独立するケースです。これは奉公人が「丁稚→手代→住み込みの番頭→通い番頭」として勤め上げたあと、元手銀を受け取って主家からのれん分けをしてもらい、別に店を構えることを許されるケースです。
奉公人が別家として店を構えると独立した商家とみなされますが、別家は毎月朔日(一日)と十五日には、本家にご機嫌伺いをすることが慣わしとなっていました。
商家における男女間での区別
「表の奉公人」と「裏の奉公人」
主筋と奉公人の間には、現代では「差別」とも言える区別があったわけですが、男女の性別の違いでも現代では「差別」と言える区別が存在しました。
その1つが「表の奉公人」と「裏の奉公人」の区別です。
ここでいう「表の奉公人」とは「店で働く男性」であり、「裏の奉公人」と「主筋のプライベート空間で働く女性」という意味です。
女性の奉公人は一人前の待遇は受けられなかった
まず「女衆」は「おなごは一生鍋の底を磨いて終わる」と言われたように、女性の奉公人は店で働くことは許されていませんでした。そのため彼女たちは店に立ち入ることさえはばかれたほどです。
よって男性の奉公人であれば、丁稚のときに店の年長者から「商売往来」などを使って教育を受けることができましたが、女性には商業のために必要な知識を授けられることはありません。
男性の場合、丁稚から手代に昇格すると一人前の扱いを受けましたが、女性は奉公に上がっている間は一生一人前の待遇を受けることはありませんでした。
「あきない世傳(せいでん)金と銀」では、幸があまりにも優秀であったため、番頭の治兵衛が「商売往来」の講義を受けること認めます。しかしこの事例は当時の感覚では、例外を飛び越えて「非常識」という扱いであったと言えるでしょう。
女名前禁止(おんななまえきんし)
奉公人に関する区別ではありませんが、主筋でも男女間の区別が存在しました。その1つが「女名前禁止」です。
江戸時代中期の大坂では、原則として女性が商家の当主となることは、仲間うちで禁止をしていました。現代の感覚からすると、「女性は社長になってはいけない」などと口にするだけでも、その会社や業界は世間から猛烈な批判を受けるでしょう。しかし当時の大坂の商家では「女名前禁止」が常識でした。
ただし「女名前禁止」という決まり事は江戸には存在せず、大坂においても当主が急逝しすぐに後継者を決められない場合は、時限的に女性が当主を名乗ることが許されていたようです。